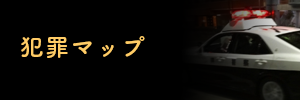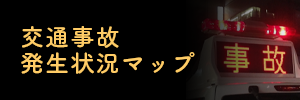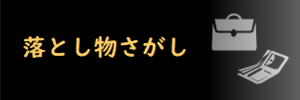本文
災害への備え(ダウンロード資料あり)
地震や風水害から身をまもろう
災害の備えは大丈夫!?
「令和6年能登半島地震」では、震度7の地震が発生し、これに伴って津波や大規模火災も発生するなど過去に類のない大災害となりました。熊本県でも過去に、震度7を2回観測した「平成28年熊本地震」や線状降水帯の停滞により記録的大雨となった「令和2年7月豪雨」など多くの尊い命が失われる大規模な災害が発生しています。
過去に大きな被害を受けていない地域であっても、大規模な災害が発生する危険性は十分に考えられます。日頃から、食料や生活用品等の準備や避難要領を確認するとともに、家庭や職場などで災害について話し合い、災害時にどのように行動するかをイメージして「自らの命は自らが守る」という意識を持ちましょう。
1 地震への備え
どんなに日ごろ冷静でも、非常時には動揺してしまうものです。落ち着いて行動ができるよう、次の「10か条」を頭に入れておきましょう。
地震から身を守る10か条
まず我が身の安全を
すばやく火の始末
戸を開けて出口を確保
火が出たらまず消火
あわてて戸外へとび出すな
狭い路地や塀ぎわ、川べりには近づかない
山くずれ、崖くずれ、津波に注意
避難は徒歩で、持ち物は最小限に
協力しあって応急救護
正しい情報を聞く
2 津波への備え
津波から身を守る最大のポイントは「逃げる(避難する)」ことです。大きな被害が出る前にすばやく高い場所へ避難しましょう。
日頃の備え
避難の準備
- 早めの避難を心がける
- 避難場所や高台の位置、避難経路を確認
- 保存の効く食糧、飲料水、救急用品等をまとめた非常用持ち出しバッグの準備
津波が発生しそうなときは・・・
- 地震の揺れがおさまったら、すぐに高台や津波避難場所へ避難
- 海岸からより高く、より遠い場所へ避難
- 原則として、徒歩で避難
- 避難後も、第2波、第3波に注意
- テレビ、ラジオ、インターネット、防災行政無線などから正しい情報を入手
3 風水害への備え
毎年のように日本列島に大きな被害をもたらす台風や大雨は、ある程度襲来時期や規模を予測できます。ふだんから気象情報に十分注意するとともに、万全の対策を講じておきましょう。
日頃の備え
防災情報の収集
- テレビやラジオ、インターネットなどから、気象台の発表する最新の情報を入手
- 地域の危険個所や避難経路などをあらかじめ確認
雨がひどいときは・・・
明るい時間に早めの避難を心がける
※ 避難時の注意点
- 安全で動きやすい服装で避難(長靴よりもスニーカー)
- マンホールや側溝などに注意
- 隣近所で声を掛け合って避難
- 病人や高齢者は背負って避難
- 子どもは手をつないだり、ライフジャケットなどをつける
- 外に避難することが危険な場合は、建物の2階などの安全な場所へ避難
4 避難のポイント
- 避難とは「難」を「避」けること
安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません - 避難先は小中学校・公民館だけではありません
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう - 市町村が指定する避難所等が変更・増設されている可能性があります
災害が起こる前に市町村のホームページ等で確認してください - 豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です
やむを得ず車中泊をする場合は、周囲の状況を十分確認してください
※ 感染症予防にマスクや消毒液などを携行してください
5 熊本県警察の災害対策
熊本県は、その地理的、気象的条件から地震、台風、大雨等による自然災害を受けやすい環境にあります。また、活火山である阿蘇山があり、噴火による被害も懸念されます。これらの災害に対処するため熊本県警察では、「平成28年熊本地震」など、これまでの災害対応から得られた教訓を活かし、平素から防災関係機関等と緊密な連携を図り、災害危険箇所等を把握するとともに災害警備計画の策定、災害警備訓練の実施、活動に必要な装備資機材の整備充実等に努めています。
また、災害が発生した場合には、人命を第一として、情報収集、救出活動、避難誘導、緊急交通路の確保等の災害警備活動を迅速に行います。
6 ダウンロード
災害対策に万全を期すには、事前の備えと、発生時の適切な行動が重要となります。
災害対策に関する資料のダウンロードはこちら
↓
防災シニア(A3サイズ)【印刷用】 (PDFファイル:325KB)
防災シニア(A3サイズ)【確認用】 (PDFファイル:357KB)
防災女子(A4サイズ)【印刷用】 (PDFファイル:289KB)
防災女子(A4サイズ)【確認用】 (PDFファイル:262KB)
【日本語】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:312KB)
【英語】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:316KB)
【中国語:簡体字】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:406KB)
【中国語:繁体字】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:406KB)
【タガログ語】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:316KB)
【ベトナム語】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:377KB)
【インドネシア語】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:316KB)
【クメール語】チェックリスト(災害への備え) (PDFファイル:597KB)