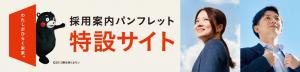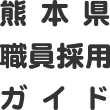本文
心理判定員(精神保健福祉センター)

所属
精神保健福祉センター
現在の業務内容
私が勤務する精神保健福祉センターは、主に18歳以上の県民の方々から、こころの健康に関するよろず相談に対応する行政機関で、都道府県と政令市に必ず1か所あります。
私のメイン業務は依存症相談で、依存症回復プログラム、家族教室などグループプログラムのファシリテートもしています。地域の保健師や医療機関との連携は日常茶飯事で、ケースワーク力も求められますが、変化に富む毎日は、とても充実しています。
依存症の背景には、幼少期からの生きづらさ、孤独な苦悩があり、誰にも頼れずに生き抜いてきた人生があります。非難されやすい依存症者を正しく理解し、依存してきたものを手放し新たな人生を歩むお手伝いは、人を理解する心理士(師)の役割として、私が最も惹かれたテーマです。

働き方や制度の魅力
私の職場は、ワーク・ライフ・バランスを重視する環境にあり、ほぼ定時で退庁できています。帰宅後は、小学生と保育園児の育児と家事に専念します。進捗ペースを自分で調整できる業務が多く、また、子どもの通院や急なお迎えが必要な際には、子の看護休暇(1時間単位)などの特別休暇も活用できるため、子育て中の私には働きやすい環境です。妊娠の際は職員に祝福してもらい、育児休暇は2年取得。産後は子どもとの時間をゆっくり過ごし、復職への不安を抱くことなく、しっかり復職することができました。

未来の後輩へのメッセージ
心理士(師)は今や、1対1でのカウンセリングだけでなく、関係機関との連携、地域や学校、企業での講師など、心理支援の対象、活動の場はますます広がっています。県の心理職は、公的機関勤務なのでカウンセリング料をいただくことはありませんが、その分、本当に過酷な状況にある相談者に関わる最前線にいます。
一方で、無料で気軽に出会える県民のためのカウンセラーでもあります。転職しなくても、子どもから大人まで、児童福祉、療育、精神科医療、メンタルヘルスと、多岐に経験できます。バラエティ豊かな県の心理職の世界に、あなたも飛び込んでみませんか?
(1月15日)